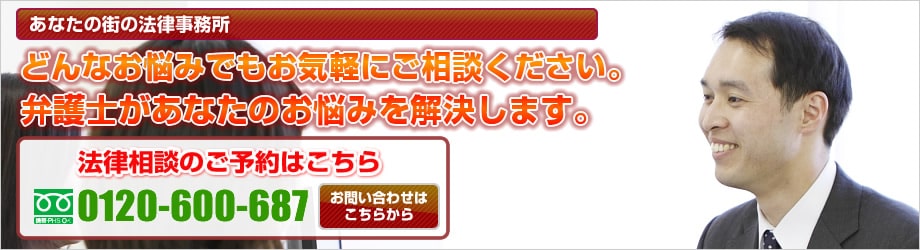更新料に関する最高裁判例
更新料に関する最高裁判例について-1
最高裁判決 平成23年7月15日判決・更新料条項は原則有効
平成23年7月15日に賃貸借契約の更新料条項の有効性に関する最高裁判決がでました。
本判決では、
「賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが相当である」として、更新料条項を原則として有効としています。
本判決では、更新料は賃料の2ヶ月分、更新期間は1年間でしたが、更新料の額や更新の期間によっては、消費者契約法に違反して無効になる可能性も残されていますので、ご注意ください。
現在、更新料の特約がない賃貸借契約を締結している場合には、この判決によっても、賃借人が契約内容の変更に同意しない限りは、更新料の支払いを求めることはできません。
また、更新料の特約がある場合であって、賃借人の同意なく、更新料を増額することや、更新期間を短くすることはできません。
更新料に関する最高裁判例について-2
賃借人が退去する際に、賃貸人が、賃借人から賃貸借契約締結時に預かっていた保証金の一部から一定額を控除して賃借人に返還する、いわゆる敷引き特約(関西に多い特約です)の有効性が問題となっていました。
最高裁判所は、平成23年3月24日及び同年7月12日に、それぞれ敷引きの有効性を認める判決を出しています。
平成23年3月24日判決は、 「消費者契約である居住用建物の賃貸借契約に付されたいわゆる敷引特約は、信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するものであると直ちにいうことはできないが、賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる損耗や経年により自然に生ずる損耗の補修費用として通常想定される額、賃料の額、礼金等他の一時金の授受の有無及びその額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものであるときは、当該賃料が近傍同種の建物の賃料相場に比して大幅に低額であるなど特段の事情のない限り、信義則に反して消費者である賃借人の利益を一方的に害するものであって、消費者契約法10条により無効となる」との判断基準を示しました。
そして、この事案では、①敷引金の額が賃料月額の2倍弱ないし3.5倍強にとどまっていること、②賃借人が、賃貸借契約が更新される場合に1か月分の賃料相当額の更新料の支払義務を負うほかには、礼金等の一時金を支払う義務を負っていないことなどから、敷引金の額が高額に過ぎると評価することはできないとしています。
平成23年7月12日判決は、前述の平成23年3月24日判決を引用した上で、
①賃貸借契約書では、1か月の賃料の額のほかに、被上告人が本件保証金100万円を契約締結時に支払う義務を負うこと、そのうち本件敷引金60万円は本件建物の明渡し後も被上告人に返還されないことが明確に読み取れる条項が置かれていたことから、賃借人が自らが負うこととなる金銭的な負担を明確に認識した上で本件契約の締結に及んだものといえること。
②賃料は、契約当初は月額17万5000円、更新後は17万円であって、本件敷引金の額はその3.5倍程度にとどまっているので、高額に過ぎるとはいい難いこと。
③本件敷引金の額が、近傍同種の建物に係る賃貸借契約に付された敷引特約における敷引金の相場に比して、大幅に高額であることもうかがわれないこと。
を理由に、敷引特約を有効としています。
地裁や高裁では、借主側の主張を認める判断もありましたが、最高裁で敷引特約を有効とする判断が続いたことで、賃貸人有利の流れができたといえます。
不動産問題関連ページ
不動産問題(TOP)
家賃滞納対策
建物の明渡し・立退き対策
賃料の増額・減額請求対策
更新料に関する最高裁判例